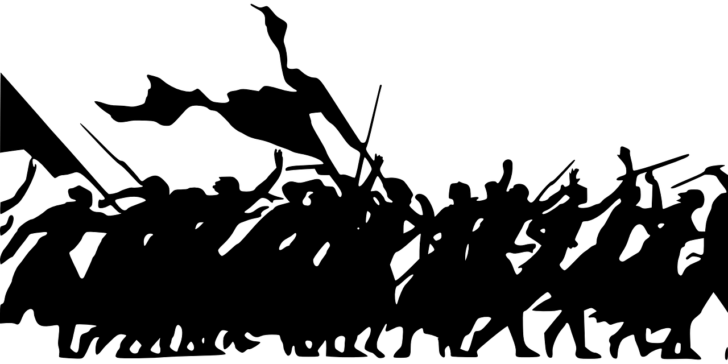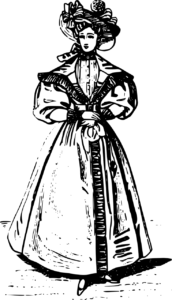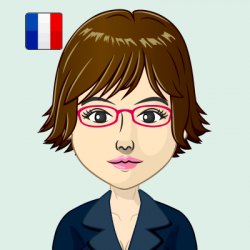最近のフランスの歴代大統領を見てみると、彼らの私生活が華やかな恋愛で彩られていることに気づきます。
エマニュエル・マクロン現大統領は24歳年上で、自分が高校生の時の国語の先生と結婚したことで話題になりました。その前のフランソワ・オランド前大統領は二度目の事実婚の間に若い女優との関係が報じられた結果、事実婚を解消しました。ニコラ・サルコジ元大統領も3度の結婚を果たし、現夫人は元スーパーモデルで歌手のカーラ・ブルーニです。
公職につきながら、私生活では頻繁に別れたり、くっついたりが自由にできるのは(マクロン大統領を除く)、結婚、離婚、同棲などのパートナーシップが個人の人生に負の烙印を押さないからです。
日本でも最近離婚率が上昇しています。しかし日本では「バツイチ」「バツニ」などの言葉が象徴する通り、日本人は一般に離婚が戸籍に記録として残ってしまうことを嫌がります。離婚して母親についた子供の姓をどうするか、などの問題もあります。
これらの問題は日本社会がまだ離婚に対して寛容でないことを示しています。
法律の点から見ると、日本では結婚か独身か、白か黒かの二者択一の選択です。フランスではその二つの間にグレーゾーンが認知され、同棲、別居、通い婚などを含む事実婚、パックス(Pacs)があります。
多様なパートナーシップがフランスで制度化されたのは一朝一夕のことではありませんでした。
フランスは従来カトリック教と君主制によって強力な家父長制が敷かれました。フランス革命は一時的にこの家父長制を弱めました。ところがその後ナポレオンが帝国を築いた頃には、この伝統的な家父長制がさらに強力になって復活しました。なぜならナポレオンは家父長制的考え方を民法として法制化したからです。
それ以後ナポレオン法典に内在する民法上の男女不平等を改正するのに200年以上の時間がかかりました。この簡単な歴史だけからでも、フランス社会が元来自由で平等な社会ではなかったことが理解できます。
今日フランス社会には多様なカップルのあり方が許容されていますが、それは女性の地位向上とともに発展してしてきました。
そのためここではフランス女性の権利伸長との相関関係から、フランスにおけるカップルの形態の多様化について説明していきます。
フランス革命以前の家父長制
中世以来拡大していったフランスの王政は17世紀後半から18世紀にかけて「絶対王政」としてクライマックスを迎えました。「絶対王政」における女性の位置付けは次の言葉に反映されています。
「わたしは、女たちは、あらゆる官職から、つまり軍事、司法、王やけの集会や評議会から遠ざけられるべきであり、女たちは、その関心の全てを、女のものとされる家庭内の仕事に向けておれば良い」(261:女性の歴史III)
女性はあらゆる公職から除外されました。この状況はフランス革命勃発後も変化しませんでした。フランス革命は、フランス人女性を政治的分野から排除しましたが、民事上は男女平等が実現しました。
ところが、それも束の間で、その後に制定されたナポレオン法典は,フランス革命以前のいわゆる旧体制の家父長制を思い起こさせるような反動的な内容に逆戻りしてしまいました。
その結果1914年に第一次世界大戦が勃発するまで、民法上は男女不平等が確立し、それは家庭内の夫婦関係の不平等の基盤となったのです。
フランス革命と女性の民事的権利
フランス革命が勃発した当初、フランスでは絶対王政が廃止され立憲君主制が誕生しました。1792年の民事法によって市民権における男女平等が部分的に実現しました。
男女とも21歳で成年とみなされ、成人女性も出生、婚姻などの承認を受けることができるようになりました。
また離婚も合法化され、法定離婚のほか、当事者の合意による協議離婚、性格不和を理由とする離婚が認められました。その結果、相続権、婚姻、離婚においてほぼ男女平等が達成されたと言ってもいいでしょう。
しかしながら、それまで続いてきた男性優位の価値観が簡単に消滅することはありませんでした。その際たる例が1791年に発布された「人権宣言」でした。
人権宣言とはフランス語でla déclaration des droits de l’homme と言いますが、この日本語の「人」に当たるhommeという言葉は、フランス語では男性、人どちらも意味する曖昧な言葉でした。
実際人権宣言の内容を見てみると、それは実質的には男性の権利の宣言と言ってもいい内容でした。なぜなら女性は男性と同等の民事的権利を獲得しましたが、政治への参加は許されなかったからです。
これは上流階級の女性にとって社会的地位の後退を意味しました。
革命勃発以前の18世紀は啓蒙の時代と言われ、貴族階級を中心とした上流階級の女性が宮廷やサロンで活躍しました。上に上流階級の女性たちは絶対王政の公職から除外されたと書きました。そうは言っても上流階級の女性たちは幅広い人脈によって宮廷で政治的影響力を発揮することができたのです。
しかし革命後これらの女性たちはそれまでの人脈による目に見えない社会的、文化的影響力を失い、中産階級以下のフランス人女性同様、家庭の良き妻、母としての役割を期待されるようになりました。一般にフランス革命が女性の権利向上に寄与しなかった、と言われる理由です。
とりわけその後の200年に及ぶ民事上の男女不平等化に著しく貢献したのが1804年に制定されたナポレオン法典でした。
ナポレオンは、フランス革命の大前提である「全フランス国民の法の前の平等」という大原則を尊重し、法の前における男女の平等は維持されました。しかしそれ以外の民事的権利に関しては、相続に関する男女の平等を除いて、女性がフランス革命期に獲得した全ての民事的権利がことごとく否定されたのです。
さらに既婚の夫婦の関係については、男女平等から男尊女卑へと変化しました。
ナポレオン法典によれば、既婚女性は「法的無能力者」として規定され「夫への服従義務」が明言化されました。妻は夫の決定について一切異議を唱えることができず、夫は強制的に妻を婚姻住所へ連れ戻す権限すら保持しました。
世帯の財産権を一方的に支配するのも夫でした。夫は自身の固有財産の管理権、処分権、および共通財産の管理権、処分権に加え、妻の固有財産すら管理する権利を得ました。それとは対照的に妻には妻の固有財産の処分権のみが与えられました。
妻が働いている場合、その給与も夫の手に渡り、共通財産となりました。夫権という名の下に、夫は妻の交際関係について詮索する自由があり、また妻の文通についても、手紙を横取りして開封し捨てることもできました。また妻が仕事に就く場合には、必ず夫の許可が必要でした。
この財産管理に関する男女不平等は1907年までおよそ100年続きました。
また1810年には姦通罪が復活しました。それによれば、結婚相手以外との貫通があった場合、妻のみ拘禁され、夫は貫通した妻とその相手を殺害しても罪を許されるというものでした。しかしながらこの姦通罪が実際に適用されることはありませんでした。
その一方で、妾との同居について、夫に対しては罰金のみという極端に不平等な扱いだったのです。
言うなればナポレオン法典の制定を期に家父長権が強化され、旧体制を思わせる男性優位の社会へと逆戻りしたのです。ちなみにナポレオン法典という名前がついていますがこのような民法を作った張本人はもちろんナポレオンでした。
ナポレオンは民法について詳しくありませんでしたが、民法草案が議論された会議を全て仕切り、活発に議論に参加しました。参加した関係者によれば、ナポレオンは専門家に劣らず争点をよく理解し、論理的に考え、正当な意見を述べたそうです。
男女の不平等を法制化するにあたり、ナポレオンは国家統一という政治的思惑を何よりも優先させました。そのためにはナポレオンは家庭内における家父長制こそ社会の安定の柱とみなしたのです。
冷徹な政治家であるのと同時に、自己の私生活において、ナポレオンは妻のジョゼフィーヌへの愛情を優先しました。
ジョゼフィーヌは過去に複数の政治家の愛人を持ったため、ナポレオンの家族はナポレオンと彼女の結婚に大反対しました。しかしナポレオンはそれを押し切って、内緒でジョゼフィーヌと結婚しました。
その一方で、ナポレオン法典が離婚を合法化している点に、ナポレオンの政治的思惑と個人的利害は一致していました。ジョセフィーヌとの間に子供ができなかったため、ナポレオンは世継ぎのことを考えて離婚を合法化した可能性があります。
離婚については、ナポレオン法典は有責主義(配偶者の一方の他方に対する犯罪、虐待、重大な侮辱など)による裁判離婚とし、破綻主義、とりわけ精神病離婚(配偶者の一方の発狂、精神錯乱)、性格不調和による離婚を認めました。十分な証拠、証人を準備して周到に落ち度について裁判所で主張しなければならず、離婚は簡単なものではありませんでした。
ナポレオンの敗退後成立した王政復古政権では、カトリックの強権的父権支配が復活し、再度フランスでは離婚が禁止されました。
20世紀におけるフランス女性の権利の確立
ナポレオン法典は1804年に発布されました。そこに規定された「良妻賢母」「家庭内の実質的男女不平等」が改正されたのは20世紀になってからのことでした。
1884年に離婚が再び合法化された後、1907年には夫が生活費、そのほかの婚姻生活を維持する費用、子供の教育費の負担義務を怠るときは、妻が裁判所に夫の賃金などの差し押さえを申し立てることができるようになりました。また夫に家事協力を求め、夫が協力しないときには強制手段も用いることが認められました。
1938年生活上妻も夫と同一の行為能力を持つことが認められ、妻の夫に対する服従義務は廃止されました。1942年の改正民法によれば「夫は家族のリーダーとして、家事と共通の利益のために職務を行うが、妻は対等なパートナーとして夫に協力すべき地位を占める。同じ独立の人格者として夫と対等な立場に立ち、ほぼ完全な自発的協力を行うことができる。」とされています。
婚姻関係にある男女の平等を確立することが最も困難だったのは、財産管理に関するものでした。この点でナポレオン法典が改正されたのは第二次世界大戦後のことでした。そしてこの財産管理における男女平等への道のりには、フランス人女性の社会進出が大きく影響しました。
100年もの間夫は妻が職業に就くことに一方的に反対する権利を有しました。しかし1965年に「妻は夫の同意なしに職業に従事する権利を有する」ことが認められました。また「夫婦のそれぞれは家事の費用の負担を請け負い、自分の収入を受け取り、それを自由に処分できる」ことも認められ、財産管理の夫婦平等が達成されました。
ナポレオン法典以来、夫婦がどこに住むかという問題についても夫が一方的に決定を下すことができました。しかし1970年に「夫婦が共同の一致によって選ぶ」ことが認められました。1975年には妻は夫と対等に「精神的にも物質的にも」家族を指導し子の育成にあたり、将来に備える権利義務があることが認められました。
フランスでは第二次世界大戦直後から女性の労働が一般化し、1970年代には共働き家族モデルが主流になりました。しかしながらカトリック教の影響が強く家父長制のもとに家族が一緒に住むという原則は生き残りました。
例えば、日本のようにお父さんが単身赴任をしてお母さんと子供は子供の教育を考えて別に別に住む、ということは一般的には考えられません。どちらかが転勤になった場合、家族が一緒にいることが優先さレルため、どちらかが仕事面で妥協するというケースが一般的です。
1975年に離婚が再度自由化されました。1884年の離婚法が定めた有責主義、裁判離婚主義が完全に廃止され、合意離婚と承諾離婚、破綻離婚と精神病離婚、一方的、双方的有責離婚などが定められ、姦通罪も廃止されました。
婚姻関係における男女平等、離婚の自由化、事実婚の一般化に伴い、1970年代に子供については父母共同親権の原則が採用され、嫡出子と非嫡出子の平等化、国籍法改正による父母の平等化、夫の居場所選択権の廃止なども認められました。
また子供の名字についても夫の苗字だけでなく、夫婦間の話し合いで決めることができるようになりました。
1980年にはさらなる平等化のもとに、世帯概念が税法から排除され、離婚した前配偶者も遺族年金を受給することができるようになりました。
最後に、フランスでは民事上の男女平等が確立しましたが、この男女平等という概念は日本人女性の立場から見ると失う面もあることを指摘しておきます。
例えば夫の浮気が原因で離婚に至ったとしても、日本のような慰謝料は妻側には認められません。フランスでは主婦をしている女性は珍しく、主婦などの経済的収入のない女性の配偶者に対する行政上の保護的措置もありません。
事実婚の増加
20世紀後半までに民法上の男女平等の原則が確立されました。その結果パートナーシップの多様化に拍車がかかりました。特に1975年の離婚の自由化に伴って、婚前同棲またはより長期的な事実婚が増加し、家族の形態が多様化していきました。
現在フランス政府は事実婚(ユニオン・リーブル)を認めて、彼らが市民生活で不利にならないよう同棲証明書を発行しています。
パックス法の成立
パートナーシップが多様化する中で、同性愛カップルの相続問題が指摘されるようになりました。同性愛者のカップルにおいて、一方のパートナーの死後、共同生活をしていた家をどうするか、という問題です。
従来の相続法によれば、この家は亡くなったパートナーの実家の両親、兄弟の間で分割されることとなります。同居人には相続の権利がないため、住んでいる家を追われるという事態もありえました。
その結果、事実婚をさらに法的に確立させたものが1999年に成立、施行されたパックス法(pacte d’association et solidaire:市民連帯契約)でした。パックス法とは国家による結婚していないカップルに対する新しい認知の仕方です。異性・同性を問わず、二人の人間が届出によって民法、税制的に、結婚に準じた扱いを受けることを目指すものです。
パックスの特色とは、その関係性が自由であるという点です。
パートナーとなる当事者二人は契約書を作成し、その内容は自由で、日常生活に関する取り決めから、パックス解消時の財産分割に至るまで盛り込むことができます。また合意のもとにいつでもパックスの契約内容を変更することもできます。
パックス法は、事実婚と結婚との間のグレーゾーンに当たります。内容は権利も義務も結婚ほど強制的なものではありません。子供は非摘出子とされ、子供には財産相続などに関して何ら権利が保証されていません。
1970年代から始まる女性の社会進出とともに事実婚が一般化して行く中で、結婚と同じ権利を求めるカップルに、不十分ながら応えたのがパックス法と言えます。
おわりにー日本との比較
これまでフランスにおける多様なパートナーシップの形態(婚姻、事実婚、パックス)について紹介しました。
パートナーシップを選べるフランス社会では、日本社会に比べて、カップルとして生きる人の割合が増え出生率向上に役立つのではないか、との疑問が湧きます。ではこの点からフランスと日本を比較していきましょう。
2011年の統計によれば、フランスの18歳以上の人口の中で、結婚をしている人は45パーセント、独身の人は41パーセントとの結果が出ています。フランスでは独身と答えた人の中に、結婚をしていないけどカップルとして様々な形態で暮らす人も含まれます。
このグレーゾーンに当たる人の割合は成人人口全体のほぼ15パーセントです。彼らと婚姻したカップルの数を合わせると、フランスでカップルとして生活している人は成人人口のおよそ60パーセントにも達します。
一方、2018年現在、日本における生涯未婚率(45-49歳と50-54歳の未婚率の平均)から類推すると、日本で結婚する人の割合は、男性で77パーセント、女性で86パーセントとなります。
日本人の男女の平均を取ると生涯既婚率は約81パーセントとなり、フランスのカップルの割合をはるかに上回っています。
ここで日仏の計算の違いを考慮する必要があります。未亡人、未亡夫はフランスでは独身者に分類され、日本では既婚者に分類されるます。その差を60パーセントと80パーセントの差に含めても、カップルとして生きる人の割合は日本がフランスを上回ると言えます。
フランスではパートナーシップを多様化させることによって、フランスの人口全体におけるカップルの割合自体は、直接増加しませんでした。
経済、社会的条件が似通った日本とフランスですが、独身で暮らす人、カップルで暮らす人の割合自体は、社会制度が異なっていてもそんなに変わりません。というか日本の方が婚姻カップルの割合は高いのです。
フランスで婚姻以外の多様なパートナーシップが社会的に認証されることによって、間接的には高い出生率(2.01)に貢献しているのは間違いないでしょう。
だからと言って、フランス政府は、出生率上昇のために多様なパートナーシップを合法化したわけではありません。
フランスにおける多様なパートナーシップは、第一にフランス国民の個人的幸福を保証するためにこそ存在します。男女不平等を明文化した人権宣言ですが、同時に「個人の幸福」が最重要であることを明言しています。
現在フランスを特徴付ける多様なパートナーシップの存在も、過去200年来のフランス大革命の帰結と考えられます。それは一人一人の市民が、社会に気兼ねなく、一番気持ちよく生きていくことができる異性、同性のパートナーとの関係性について、自由に選ぶことができる権利、と言ってもいいでしょう。
参考資料
平成22年国勢調査