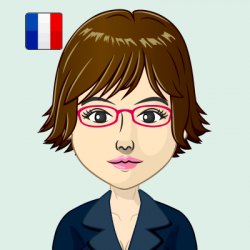フランス人男性と日本人女性が国境や文化の差を超えて、恋愛や結婚をするようになって、およそ250年。その始まりは、200年以上続いた鎖国をやめて開国した明治時代のことでした。
ここでは初めてフランス人男性とエロチックな関係を結んだ日本人女性の一人お兼とそのパートナーでその後フランスの国民的作家となるピエール・ロチの関係について紹介します。
お兼と言ってもピンと来ないかもしれません。
でもオペラの『マダム・バタフライ』(蝶々夫人)ミュージカルの『ミス・サイゴン』のモデルとなった日本女性と言えば、日本でもお馴染みだと思います。お兼とはその原作の主人公のモデルとなった実在の日本人女性です。
明治開国から間もない時代、お兼とロチはどこで出会ったのでしょうか。言葉が全く通じずに互いの文化についてもまったくわからない二人の関係とは、一体どんなものだったのでしょうか。そしてお兼はどのような経緯から、蝶々夫人、ミス・サイゴンへと繋がって行ったのでしょうか。
お兼とピエール・ロチ(Pierre Loti)
お兼は1885 年に故郷の長崎市でフランス人の船乗りと出会います。名前はピエール・ロチ。
ピエール・ロチという名前は今日の日本ではあまり馴染みのないフランス人かもしれません。
ロチは19世紀末には、フランスはもとより世界的に人気を博した(当時の世界とは欧米社会を指す)作家でした。本国フランスにおいてロチは41歳の若さで、作家としては最高の地位、アカデミーフランセーズの会員に任命されたほどの一流の作家でした。
ロチの小説は独特の哀愁と甘美な異国情緒を放つその文体に特徴がありました。それはロチが二つの職業を持っていたことに由来します。
ロチは作家である前にまず海軍軍人でした。そのため当時一般のフランス人が成し得なかった世界旅行に出かけることができました。
ロチはヨーロッパ以外の地域、コンスタンチノープル、タヒチ、セネガル、日本などを軍艦で訪れ、現地の女性との恋愛を通じてその土地の風習を知り、それを小説として表現しました。
ロチが描く異国情緒あふれる『楽園的生活』は同時代の印象派のゴーギャンの『タヒチの女』などの絵画に似ています。エキゾチックな女性の描写は19世紀後半から20世紀初頭にかけて、植民地帝国フランスが拡大しつつあった時代に特徴的なテーマです。
ロティは軍人として二度日本を訪れました。一度目は1885年、二度目は1900-1901年のことです。
南の国の官能的な恋愛小説を得意とするロチにとって、喜怒哀楽を表に表さない日本人はそれだけで物足りない存在でした。さらに当時の多くの欧米人と同様に、ロチにも欧米社会以外の国を見下す傾向がありました。
そのためロチの日本に対する態度も好意的なものではありませんでした。
この点が江戸時代から明治時代にかけて活躍した親日家のラフカディオ・ハーン、シーボルト、そしてクーデンホーフ・カレルギー伯などの西欧人とロチが決定的に違う点でした。腰を落ち着けて日本を知ろうと努力するのではなく、日本はあくまでも通りすがりの国だったのです。

当時欧米ではまだ日本の実情がよく知られていなかったため、ロチは後で日本について書けばお金儲けになると考え『お菊さん』という小説を書いたと告白しています。
明治日本、19世紀末のフランス、そしてジャポニズム
なぜロチは日本がお金になると考えたのでしょうか。そのきっかけは当時のフランス、欧米における日本美術ブーム、すなわちジャポニズムでした。
19世紀後半から20世紀にかけて、ヨーロッパの主要都市では万博が開催されました。そこでは国際貿易を伸長するために、欧米以外の異国の文化、工芸品、美術が幅広く紹介されました。
日本は欧米諸国の植民地ではありませんでした。しかし日本人もヨーロッパ各地の万博へ招待され、日本の伝統工芸品が広く知れ渡るようになりました。実際江戸幕府末期から明治時代にかけて、日本の様々な工芸品、浮世絵、着物などが大量にフランスへ輸出されるようになりました。
当時のインテリ階級の間では、日本の品々をコレクションして家に飾ることが流行しました。
ゴッホやマネなどの印象派の絵画を見ると、肖像の背後に日本の品々が描かれていたり、キモノをまとった西洋の女性が描かれたり、と日本趣味には事欠きません。また日本の工芸品は、絵画以外にも花瓶、家具などにも応用され、アール・ヌーヴォーが誕生しました。
旅行が自由にできない時代、日本好きのインテリ層のフランス人男性は、浮世絵、着物、漆器、陶芸品などの日本独特のモノを通じて日本についてのイメージを膨らませました。またフランスの一般市民も、日本の品々が描かれた印象派の絵画、浮世絵、着物などを目にする機会が増えました。
このような状況で、小説家のロチは日本について小説を書けばお金になると考えました。
1885年に初来日したロチは長崎に一ヶ月ほど滞在しました。当時の日本は開国して文明開化、西欧化が進みつつありました。しかし大半の日本人は人力車、お歯黒、着物などの伝統的な風習の中で生きていました。
その一方で、当時のフランスは世界的に見て最も文明が進んだ国の一つであり、自動車、カメラなどの文明の利器も出現し始めました。

ロチ自身は中産階級の出身でしたが、彼はヨーロッパの上流階級の名残が残る誇り高きフランス海軍士官となりました。
そんなロチにとって、いくらフランスでジャポニズムが人気を博しているとはいえ、真夏の長崎で木と紙でできた家で暮らしながら目に入ってくる日本の風物を見て、前近代的と感じたことでしょう。
例えばロチは「ヨーロッパ人男性が歩いていると、十五歳前後の若い娼婦たちが寄ってきて売春を促した」と日記に書いています。
この頃フランスでは女子の初等教育の義務化が始まっています。通りで10台半ばの若い女性たちが娼婦として群がってくるというのは、当時のフランスではありえない状況でした。
ロチが初来日した時、彼は35歳で独身でした。日本に到着するやいなや外国人との婚約、結婚の仲介をする日本のエージェントを通じて、日本人女性を紹介してもらいました。
彼女の母親、姉妹、叔母に加え、ロチの家主の家族が見守る中当時の日本の習慣に従ってロチは「1ヶ月毎に更新する条件付きの結婚」を果たし、それは地方の警察にも登録されました。ロチの日記によれば、18歳の相手「お兼さんは恥ずかしそうにして、目を伏せていた」そうです。
この「結婚」というのは、当時の日本やフランスの結婚とは異なるものでした。
結婚というと聞こえはいいですが、要は、国を介したオフィシャルな愛人契約でした。ロチの乗っていた船には4人の船員がこの1ヶ月の結婚を果たしたそうです。
ちなみにロチは日記に「結婚した」と書き記しながら、毎月20ピアストルをオカネ・サンの親に支払う、という条件については何も書き残していません。
そのため今日フランス版のWikipediaのピエール・ロチの記事を読むと、ロチがお兼と正式に結婚したというニュアンスで紹介されていますが、これは明らかに間違いです。この記事を書いた人は多分当時の事情について知らずに、ロチの日記の言葉尻だけ捉えてこの記事を書いたと想像されます。
ロチの日記から読み取れるオカネ・サン
ロチは日本ひいきではなく、日本に対してとりわけ関心を持っているわけでもない、通りすがりのフランス人でした。
ロチの日本に対する態度は、フランス、ヨーロッパの大半の人々と同じものであるため、ロチの書く小説も多くの西欧人の共感を呼びやすい内容となりました。
ロチとお兼の間には、言葉、文化の違いに由来する大きな心理的壁が存在したことは当然予想できます。実際二人は物理的に一緒にいても意思疎通をはかるすべを何も持ちませんでした。
ロチは日記の中でしばしばお兼をモノに例えています。それは屏風や茶碗の絵だったり人形だったりします。
『オカネ・サン、この小さなオカネ・サン、僕はその絵姿を、屏風や茶碗の底など至る所ですでに見てきた。人形のように愛くるしいこの顔、なめらかでうわぐすりをかけたような漆黒のこの美しい髪、淑やかなお辞儀のためにいつも前屈みになっているこの特殊な物腰、背中で大きく膨らませて結んだこの絹でできた帯、広い幅の垂れるこの袖、脚の下に張り付いて、トカゲの尻尾のような引裾を作るこの着物・・・この陶磁器の小僧と向き合って一人で家にいると、僕は泣きたいほど悲しくなるのだ。』(27−28頁)
あたかも浮世絵に描かれた日本人女性がそのまま見た目だけ文章化されたかのようです。以下はお兼さんが昼寝をしていた時の状況です。
「オカネ・サンは畳の上に腹ばいになって昼寝をしていた。高い髪とかんざしが長く伸びた寝姿の上に突き出し、着物の小さな引袖のためにほっそりした体がさらに長く延びた。十字に伸ばした腕は、羽のように広がっていた・・・。」(48頁)
オカネ・サンの母親が見かねてオカネ・サンを起こそうとするとロチは言いました。
「カカ・サン、そのままにしておいてやりなさい。この女はこうしている方がずっと僕の気に入っているのだから!」
「この小さなカネが、いつも眠っていることができないのは残念なことだ。こうしていると彼女は装飾にうってつけだし、それに少なくともぼくをうんざりさせない。ぼくは確かにこの人形の頭の中で起こっていることを深く知るまでには、まだ彼女の国語がよく話せない。そしてとどのつまり、その頭の中では何かが起こっているのだろう。だが、それを知ろうとする興味はぼくにはないーそれはぼくにとってどうでもいいことなのだ。」
お兼は自ら進んで感情を表に表すことをしないタイプの日本人女性でした。ロチはそれに対して不満、苛立ちを募らせていきます。
しかしたった1ヶ月の日本滞在で、もともと関心のない日本人女性と本当に意思疎通をすることを望んでいたとは考えられません。
ロチの苛立ちには、彼がこれまで体験してきた南国と日本の事情が異なることも関係していると思われます。彼は南国の女性と日本人女性の違いを次のように比較しています。
「ここにあるものは全て何かが欠けている。正気のない真似事に過ぎないというべきだろう。そしてぼくはもの悲しく自分にこう問いかけるー夏の輝かしさとは本当にこんなものでしかないのかー。」(49頁)
ロチは、他の南国と同様、日本の暑い夏に見合う情熱的な恋愛を期待していました。それは男性中心的な性愛を中心とした恋愛と言ってもいいでしょう。しかしその期待が叶わなかったからこそ日本、日本人女性への失望がさらに深まっていったのです。
ロチの目から見ると前近代的に見えた長崎での生活ですが、当時の日本は世界的な資本主義体制の中に組み込まれつつあり、近代化が急速に進んでいました。その点が日本とロチが訪問したそれまでの異国とが異なる点でした。
資本主義は全ての関係をお金を介した関係へと変えて行きます。ロチとお兼が金銭によって繋がっていることが、何よりもそれを象徴しています。
ロチは確かにこれまでにも様々な異国女性との体験を小説にして来ました。しかし日本では、ロチはお金を支払って「一ヶ月ごとに更新する結婚」という名の売春を買いました。
ロチは自分自身のこの行為をどう感じていたでしょうか。プロテスタント教徒として、少なからず罪悪感を覚えたのではないでしょうか。
本国フランスでは、同じ屋根の下に暮らす女中に手を出すということはありましたが、18歳の若い女性を金で買って結婚という名目のもとに一緒に暮らす、などということはありえない状況でした。
ロチは、自分の欲求が満たされない不満を、市場主義経済におけるお金を介した男女の関係性にではなく、お兼の非社交的な態度に起因させました。そしてお兼を、女性、人間として見るのではなく、彼女があたかも景色の一部であるかのように扱ったと考えられます。
ロチは、お兼を非難することによって、お金で擬似的な愛情を買ってそれを小説にしてお金を儲けようとする自分自身に対するやましさから目を背けたと考えられます。
お兼の気持ち
では当時18歳のお兼はロチに対してどのような気持ちだったのでしょうか。
これについてはお兼自身が記録を残していない以上本当のところはわかりません。そのためここではロチの日記から類推される、女性としてのお兼の気持ちについて想像してみます。
お兼は、確かにロチが書いたように、平均的日本人女性以上に内気で無口だったことでしょう。でもそれはお兼は近代的で、シニカルな感覚も持ち合わせていたからとも解釈できます。

ロチによれば、タヒチなどの南の島の女性は、少なくとも自分の性的欲望については正直に表現し、自分を相手に委ねたといいます。
ロチはお兼が同じように振る舞わないことに苛立ちを感じたのです。
しかしお兼としては、自身の人としてのプライド、羞恥心から、もしくはロチを好かなかったという理由から、自分の欲望、感情をロチに明け渡さすことをよしとせず、逆に蓋をしたと考えられます。
お金を介した男女の関係としてみれば、ロチとお兼の関係は近代的なもので、現代社会でもよく見かける関係となります。
お兼のプライドとお金
さてお兼との擬似的な婚姻関係は、ロチが一ヶ月後長崎から出航することであっけなく終わりを告げます。このシーンは小説『お菊さん』のクライマックスとして再現されていますので、ここで紹介します。
主人公のフランス人男性は、お菊さんに長崎を発つことを告知するために、足音を忍ばせつつ住居の二階へと上っていく。案の定お菊さんは、彼の存在に気づかず、彼からもらったお金がにせ金かどうか投げて確かめていた、という光景です。
このシーンは架空のもので、ロチの創作だと言われています。それはお兼の実際の態度ではなかったのです。ロチの日記によれば、実際のところは「私の手を彼女の手のなかに包み込んで、ちょっと悲しげに握りしめた」ということです。
別れに際しての、お兼の態度は日本人から見ると違和感がありませんが、ロチからみると、他の異国女性の態度とは大きく異なっていました。涙ひとつこぼさずに泣き顔も見せないオカネ・サンの態度に面して、ロチは少なからずプライド、自尊心を傷つけられました。
その結果、ロチはリベンジを果たすために、実際のお兼とは異なるイメージを創作しました。そして「金だけが目当て」の人間的感情の欠如した日本人女性を小説「お菊さん」に描きました。

このラストシーンからも、ロチがお金が介在するお兼との関係に罪悪感を持っていたことが想像されます。
その後、ロチはフランスに戻り、スペインとの国境沿いのバスク地方出身の若い女性と結婚し、4人の子供の父親となり、幸せに暮らしたということです。
ロチは自分の妻と愛人を明確に区分けする。当時のフランス人男性としては典型的なタイプでした。
ロチの日本人、日本人女性を見下したかのような小説『お菊さん』はしかしながらフランス、ヨーロッパで大反響を巻き起こしました。そしてその後美しい悲劇『蝶々夫人』へと生まれ変わりました。ちなみに『蝶々夫人』は1904年にヨーロッパで初上演されました。
このオペラの中で、守銭奴的なイメージのお菊さんは、彼女とは真逆のイメージの日本人女性、蝶々夫人に取って変わられました。蝶々夫人は、長崎を舞台に、アメリカの海軍士官に裏切られ、何年も相手の帰りをひたすら待つ日本人女性として描かれました。
それは相手を無条件で一方的に待つことを厭わない、ひたすら受け身で、感情の面では自分が与えるばかりの、日本人女性のイメージです。
哀愁漂うプッチーニの音楽に乗って、その後長らく西欧社会に定着することとなった日本人女性のステレオタイプが誕生した瞬間です。
終わりにーオリエンタリズムの視点からロチを読む
最後に、なぜロチの小説に描かれた守銭奴的日本人女性は姿を消して、相手を見返りなく愛し、ひたすら受け身で待つばかりの日本人女性のイメージが生まれたかについても考えてみましょう。
もちろんその方が悲劇のストーリーとして説得力があり面白いから、というのが一番大きな理由です。それに加えて「時代」も大きく影響しています。
19世紀末から20世紀にかけて、ヨーロッパでは東洋の美術、工芸品、そして演劇などを愛好する東洋趣味が流行しました。
これは一般的にジャポニズム(日本趣味)と言われますが、ジャポニズムは広い意味でオリエンタリズムの一部でした。
オリエンタリズムとは、西欧による、西欧とは異なる東洋を含めたオリエントの文化、文明に対する美的、審美的崇拝の態度を指します。
まさに異国情緒がつまった日本の浮世絵などの美術は西欧による美的、審美的賞賛の一例でした。
同時にその背後には政治的力関係も作用していました。なにしろこの時代は西欧列強による植民地化が進んだ時代です。
その結果オリエンタリズムとは、当時の西欧人が、西欧以外のオリエントを美的、文化的には愛でても、政治的、知的には見下した態度を指します。
そしてロチの小説にはこのオリエンタリズムに内包されるダブルスタンダードが見事に表現されています。
フランス人男性のロチは当時の植民地帝国として『優勢』なフランスを、日本人妻のお兼はフランスと不平等な外交関係を受け入れざるをえない『劣勢』な明治日本の立場を反映している、とも考えられるからです。
小説『お菊さん』に表象されたロチとお兼の関係については、日本ではこれまでロチがお兼を個人的に好かなかった、ロチが親日ではなかったためにそれが小説に反映されてしまった、などとロチの性格を中心に説明されてきました。
しかしながら、ロチとお兼の関係は実際には資本主義社会に特徴的なお金を介した男女の微妙な関係、そして欧米諸国による非欧米諸国の植民地化に象徴する政治的力関係の優劣によって特徴づけられてもいたのです。
そしてお金を通じた愛人関係は受け入れても真の感情の交流を頑に拒んだ日本人女性(お兼)から、支配と同時に感情的にも相手に翻弄され続けることを自ら選んだ蝶々夫人へと変化していきました。
その結果美しいオペラが誕生したのです。しかし同時にこのような日本人女性であるところの悲劇のヒロインは、西欧人が望む日本のイメージであったのです。
オペラ、ミュージカルなどに表現されたアジア、日本のヒロインと西欧の男性の恋愛関係を楽しむ際には、どうかこれらの歴史的背景も思い起こしてくださいね。
参考文献 ピエール・ロチ お菊さん (野上豊一郎翻訳)岩波書店
船岡末利 ロチの日本日記ーお菊さんとの奇妙な生活 有隣新書